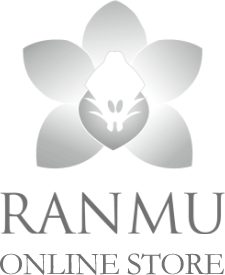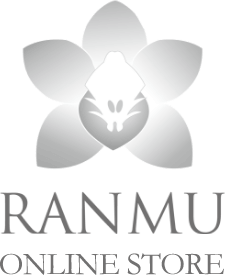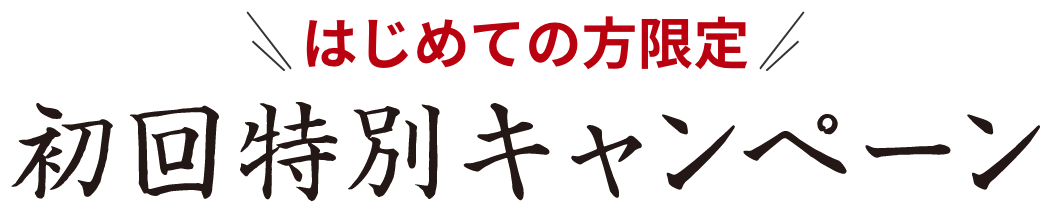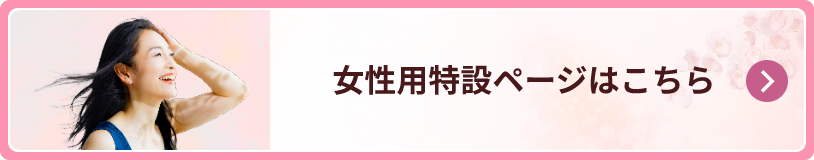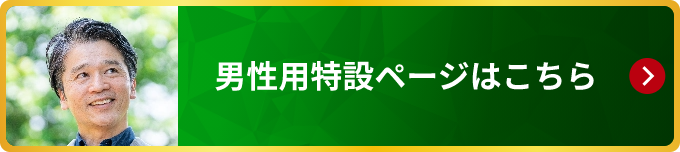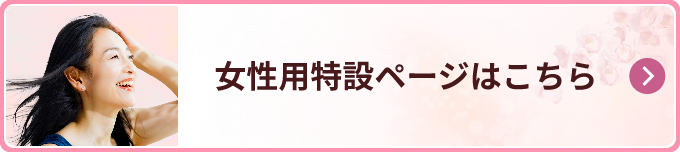お酒と薄毛の関係について
育毛お役立ちコラム
2022.11.21
飲酒は薄毛の原因になると言われていますがアルコールを飲む機会が多いと、髪の毛に悪影響なのではと不安を覚える方も多いのではないでしょうか。
では、アルコールは実際に髪にはどのような影響があるのでしょうか。また、お酒とうまく付き合いながら、薄毛を予防する方法はあるのでしょうか。
目次
- 1.お酒が薄毛の進行に及ぼす影響
- 1-1.髪の成長に必要な栄養素が不足しやすくなる
- 1-2.血行不良
- 1-3.頭皮の乾燥を招く
- 1-4.睡眠の質の低下
- 2.お酒と上手く付き合っていくには
- 2-1.ストレスをためないよう適量を守ろう
- 2-2.1日の適量とは
- 2-3.休肝日を作ることが大切
- 3.まとめ
\ 蘭夢を使って髪に自信を取り戻す /
おすすめの育毛剤を見る
お酒が薄毛の進行に及ぼす影響
髪の成長に必要な栄養素が不足しやすくなる
アルコールが及ぼす髪の直接的な影響としては、アセトアルデヒドと呼ばれる物質が関わってきます。体内に取り込まれたアルコールは、胃と小腸で吸収され、肝臓でアセトアルデヒドという物質に分解された後、身体に無害な物質に分解されます。
このアセトアルデヒドは、飲酒で顔が赤くなったり、動悸が激しくなったり、頭痛・吐き気・眠気などの症状の原因となる毒性の強い物質で、血液中の栄養や酸素を押しのけてしまう性質を持っています。
過剰な飲酒で分解が追いつかなくなると、不足を補うためにアミノ酸が動員されます。アミノ酸は髪の成長に欠かせない栄養素です。アセトアルデヒドの分解に多くのアミノ酸が必要とされれば、その分だけ髪に行き渡る栄養素が不足しやすくなります。
血行不良
飲酒によって懸念されるのが、糖質の過剰摂取です。また、飲酒だけでなくおつまみによる糖質の過剰摂取も考えられます。
また、日本酒・ワイン・梅酒・ビールといったお酒はカロリーや糖質量も多いので、糖質の過剰摂取により中性脂肪が増え、血液がドロドロになり血行不良となります。
これによって頭皮も同様に血行不良を起こしてしまいます。髪の毛への栄養は血液を通じて供給されるため、栄養が十分に行き渡らず育毛を妨げてしまう原因となります。
そして結果的に髪の毛が十分に成長することができず、薄毛の原因へと繋がるのです。
頭皮の乾燥を招く
お酒には利尿作用があるため、飲み過ぎにより脱水症状を起こすことがあります。
体の水分が奪われると頭皮も乾いてうるおいをなくしてしまい、赤みやかゆみといった症状につながります。酔っていることもあって、つい頭をかいてしまうと地肌が荒れて、抜け毛が増えてしまうことがあります。
睡眠の質の低下
アルコールを飲むと寝つきが良いという方もいらっしゃると思いますが、アルコール分解時に発生するアセトアルデヒドは、睡眠の質を低下させるといわれています。
寝る前にお酒を飲むと、夜中に目が覚めたり睡眠の質が低下したりして、睡眠時間は足りているのに眠気や疲れがとれなくなります。
質の良い睡眠は、髪の成長に必要な成長ホルモンの分泌に欠かせないため、就寝前の飲酒は髪の成長を阻害する要因になってしまうので注意が必要です。
お酒と上手く付き合っていくには
ストレスをためないよう適量を守ろう
禁酒をしてお酒を飲まなければアセトアルデヒドの摂取は抑えられるため、悪影響は避けられます。
また、お酒を飲まなくなることで睡眠の質も期待できるため、生活改善による二次的な効果が出てくるでしょう。
ただし、髪の健康を考える人は禁酒するべきとも言い切れません。好きなお酒を無理にやめてしまうことで、ストレスがたまってしまうかもしれないからです。
禁酒によりストレスを感じることで自律神経に乱れが生じたり、筋肉が緊張して血管に収縮を引き起こしたりするため、血流が減少して次第に血行が悪くなっていきます。また、自律神経の乱れは内蔵機能の低下にも繋がります。食欲不振で消化不良になり、食欲が減退していくと、栄養摂取にも影響が出てしまいます。
薄毛を気にしているのであればお酒はほどほどに、節度を持って楽しみましょう。
1日の適量とは
厚生労働省の示す指標では、節度ある適度な飲酒は1日平均純アルコールで20g程度の飲酒ということになります。アルコール20gとは大体「ビール中ビン1本」「日本酒1合」「チューハイ(7%)350mL缶1本」「ウィスキーダブル1杯」などに相当します。
また、女性は男性に比べてアルコール分解速度が遅いといわれている為、飲酒量は男性に比べて少なくすることが推奨されています。65歳以上の高齢者の方についても、アルコールの分解速度が下がることや、血中濃度が高くないにもかかわらず酔い方がひどくなることなどが示唆されていますので飲酒量は少なくしたほうがいいでしょう。
休肝日を作ることが大切
肝臓の機能には個人差があるうえに、加齢とともに低下する傾向があります。そのため、飲酒を楽しむためにも休肝日を作ることが大切です。
肝臓を休ませることで、アルコールの分解に追われて肝機能が低下する事態を防げる可能性があります。休肝日は週1日以上設けることが大切です。
まとめ
薄毛は遺伝だけの問題ではなく、生活習慣などの影響や関係性など、さまざまな要因が考えられます。飲酒が薄毛の原因になると言われていますが、薄毛に悩んでいるからと言って必要以上にお酒を遠ざける必要はありません。適量のお酒をたしなむ分には頭皮や髪に悪い影響を与えることはほとんどありません。
頭皮や髪にとっても大切なのは、心身共に健康であることです。
お酒の飲み過ぎは健康そのものを損ない、食事が偏りやすくなり、十分な睡眠もとれなくなって健康な髪の毛の成長を妨げるので、量や頻度に注意しながらお酒と上手に付き合っていきましょう。
記事監修
毛髪診断士:細堀由香